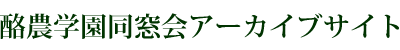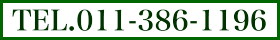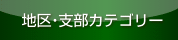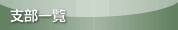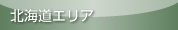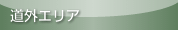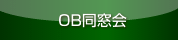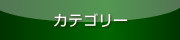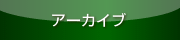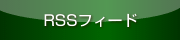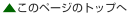OB会新着情報一覧
酪農学園短期大学昭和40年度入学生クラス会の開催報告
 厳しい教育環境の中で我が母校の努力に感謝と敬意をいたします。
厳しい教育環境の中で我が母校の努力に感謝と敬意をいたします。
日本の農業界における活躍また道内での卒業生も農村等を含め日夜活躍をしております。
我が42年3月22日卒業以来クラスメートとの交流をしておりますが此の度、下記のとおり14名の出席者により岡山県新見市、岡山市においてクラス会を開催いたしました。
学園の方からは坂本与市先生をお迎えし、楽しい2日間でありました。
卒業以来43年ぶりにあった者もおり、其々感無量の2泊3日の限られた時間ではありましたが又の再会を誓い無事終えました。 以上報告します。
昭和40年度酪農学園短期大学入学生クラス会
日 時 : 2011年10月19日(水)~21日(金)
会 場 : 19日:岡山県 新見市・グランドホテル みよしや
20日:岡山県 岡山市・東横イン西
(文責 伊田 新一)
野幌機農高等学校 昭和36年卒業 同期会開催報告
 機農高校農業科第17期生、農村経済科第5期生の同期会を、平成23年10月9日(水)から20日(木)の一泊二日で札幌市に於いて開催いたしました。
機農高校農業科第17期生、農村経済科第5期生の同期会を、平成23年10月9日(水)から20日(木)の一泊二日で札幌市に於いて開催いたしました。
前回旭川地区の開催は入学から50年、3年後の本年は卒業から50年の節目を迎えての開催になりました。当日、遠くは、中国地区そして関東、東北、全道一円から43名の方々が集い、集合写真撮影後、歓談・懇親会に移り、最初に物故者に黙祷を捧げ、発起人代表新谷拓朗氏の挨拶があり、残念ながら恩師の出席は叶わなかったものの、卒業後夫々の半世紀に亘る多岐多彩な人生の歩みやら近況報告に花を咲かせました。 中締めは、次回(2年後)の開催地十勝地区を代表して鈴木洋一氏の万歳三唱で閉会。
後、二次会に移り、余興や「校歌」を合唱し一次、二次会通して全員参加の5時間に及び尽きぬ楽しい思い出のひと時を過ごし、更なる同期の「絆」を強固なものとし再会を誓い会いました。
末尾になりましたが、連合同窓会から過分なる助成金を頂き、厚く感謝とお礼を申し上げます。 (文責 和泉 建興)
緑風会 第5回 2011年度道東地区支部研修会(終了)
晩秋の候 会員各位におかれましては益々ご健勝のことと拝察致します。
さて、5回目を迎える支部研修会ですが、今年度は釧路にて実施することとなりました。
今回は、食品流通に係わる講演と改革が進む酪農学園の状況についての研修を予定しています。この機会が、会員相互の親睦を通じて、教員としての資質向上を図り、さらに多くの卒業生を自信を持って大学への進学指導できる一助となれば幸いです。
二回目となる釧路会場での開催を成功させ、今後も、酪農学園と本会を発展させるため、支部長、各校連絡員は、多数の参加に向けて案内及び集約にご尽力願います。
なお、参加の集約は、各校連絡員が11月1日(火)までにメールにてお知らせ下さい。
1 日 時 平成23年11月19日(土)
13:30~16:30 支部研集会
17:00~19:00 懇談会
2 会 場 釧路市交流プラザ「さいわい」
フィッシャーマンズワーフ「MOO」二階「港の屋台」(懇談会)
3 参 加 者 ・緑風会会員、但し、十勝、釧根、オホーツク支部を主とする
(参加者目標30名以上)
・酪農学園関係者(学長、各学科長等依頼中及び入試事務局)
4 内 容 ①講演
仮題「流通業界の現状と将来像」(イトーヨーカ堂に依頼予定)
②酪農学園大学の近況と進学について
③懇談会
5 そ の 他 今回は経費節減を図るためホテル等の会場は使用せず、公設会場を利用する予定です。また、懇談会もホテル等での宴会形式はとりません。予めご理解下さい。
①懇親会費3,500円を申し受けます。
②運営、参加者とりまとめは、準備の都合上標茶高校(西田)が窓口となります。
第13回林家卯三郎(本学獣医学科25期)一人会(終了)
11月19日(土)19時00分開演(開場30分前)、20日(日)14時00分開演。
ドラマシアターどもⅣ(江別市2条2丁目7-1 江別駅徒歩5分)において、本学獣医学科1993年度卒のOBで,当時落後研究会に所属し、現在、落語家としてご活躍の林家卯三郎(小川祐之介氏)による第13回一人会が開催されます。後援は江別市教育委員会・酪農学園大学。
初日の演台は「宿屋仇」他2席。2日目は「餅屋問答」他2席。異色OBの上方落語をご堪能下さい。詳細は下記をご覧下さい(クリックすると拡大します)。

酪農学園大学第六期酪農学部同期会開催報告
 酪農学園大学第六期酪農学部同期会を、平成23年10月7日(金)から8日(土)の一泊二日で、初めて北海道の中心“へそ”にあたる富良野市で開催しました。
酪農学園大学第六期酪農学部同期会を、平成23年10月7日(金)から8日(土)の一泊二日で、初めて北海道の中心“へそ”にあたる富良野市で開催しました。
卒業から、42年目、前回同様に多くの同期生が集えるよう農経学科と夫婦での参加等、企画しました。
遠くは、大阪、青森など道外居住者と道内各地から16名の同期生と恩師の原田先生の総勢17名が集いましたが残念ながら農経の参加はありませんが、夫婦での出席は1組ありました。
原田学園長から大学の現状、とりわけ改革の芽が結実しつつあることや、基本理念である“3愛精神”の真髄等のお話がありました。
この後、各自の報告や情報交換、社会状況の話題等、年を忘れて喧々諤々と夜遅くまで続き、次回を平成25年札幌での開催と新幹事4名にて行う事を決定しました。
翌日8日は、秋晴れの中、富良野市内のチーズ工房やワイン工場の見学を行い、昼食後、2年後の再会を約束し別れを惜しみながら無事に終了しました。
末尾ですが、同窓会連合会、酪農学科同窓会より過分なる助成を頂き、秋めく富良野での思い出を綴れた事に厚く感謝と御礼を申し上げます。(文責:富田 啓衙)
「安宅教授定年祝賀会」のご案内(終了)
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、この度安宅 一夫教授が明年3月で定年退職(勤続41年)されます。そこで退官祝賀会と5年毎の家畜栄養学・飼料学研究室同窓会を併せて開催することにしました。当日は楢崎先生も参加されます。ご多忙中とは存じますが、万障繰り合わせの上、多数参加くださいます様ご案内いたします。報告です、安宅教授を代表とするサイレージ調製法開発グループが第8回畜産技術協会賞に選定されました。なお、安宅教授の最終講義については翌年明けに予定しています。
記
日時: 2011年11月5日(土)18時~
場所: 新札幌シェラトンホテル
札幌市厚別区厚別中央2条5丁目5-25 TEL 011-895-8844
JR 新札幌駅・地下鉄 新札幌駅より徒歩5分
会費: 7,000円(飲み放題・写真代込み)
二次会も計画しています(会費別途)
宿泊: シェラトンホテルに直接お申し込み下さい。
その際に祝賀会・同窓会に出席する事を伝えて下さい。
尚、ご出席の方は準備の都合上、10月15日までに
はがき、電話、FAX、Eメールで連絡してください。
連絡先:〒069-8501 江別市文京台緑町582
酪農学園大学 家畜センター 上野光敏 宛
TEL・FAX 011-386-1564 携帯 090-2054-3462
Eメール m- ueno@rakuno.ac.jp
「安藤功一先生を偲ぶ会」のご案内(終了)
昨年12月5日に急逝されました酪農学園大学名誉教授(乳製品製造学) 故安藤功一先生(本学1期生)の没後1周年にあたり、先生を偲ぶ会が有志の企画により予定されております。詳細については別途案内状を御覧ください。
安藤先生を偲ぶ会 同窓会様案内
三愛女子高等学校 第28期同期会開催
9月3日(土)18時よりシェラトン札幌ホテルにおいて、第28期同期会が開催された。参加者数は39名。卒業後23年目に三愛会がバックアップとなり、同期生全員が参加する同期会である。もともと160名余りの卒業生数ということや、そのうち所在が判明していたのが約60名ということ、そして子育て・介護や仕事などの事情で参加者人数が心配されたが、当初見込んでいた数が集まり行われた。なお、住所未判別者も多く、現実問題として60名近くの同期生に案内が回らなかったのが残念である。
祝宴は、三愛会会長・同期会代表・卒業当時の井上昌保校長の挨拶の後、参加した卒業担任などのメッセージをいただき、和やかな雰囲気が満ち溢れる会合となった。最後には、高校時代を思い出しながら讃美歌やハレルヤコーラスを元気に声高々歌い上げ、散会となった。 (第28期代表幹事 横尾孝子)


酪農学科・農業経済学科第6期生同期会ご案内
皆様お元気でご活躍のことと存じます。
前回総会にて2~3年後に開催予定でした、同期会を2年後の今年に、初めて富良野にて開催する運びとなりました。
早いもので卒業から、42年になりました。今回以降も農経部と合同で開催する事に致しました。
是非この機会にご参集していただき、同級生や先生方に会い、懐かしい話や近況などで盛り上がっていただければと思います。
詳細はPDFでご確認願います。酪農学科第6期生の同期会ご案内
第4回緑風会研修会・懇談会報告





 9月3日(土)13時より、本学C4講義棟を会場にして、30数名の出席により第4回となる緑風会研修会が開催された。台風12号の影響、教員採用試験の関係上、例年より1月遅れでの実施となった。玉利和弘緑風会会長、原田勇学園長のご挨拶で開会した。講話では、「酪農学園の現状と課題」と題して小野寺秀一教授(入試部長)より入試を取り巻く厳しい現状報告が行われた。
9月3日(土)13時より、本学C4講義棟を会場にして、30数名の出席により第4回となる緑風会研修会が開催された。台風12号の影響、教員採用試験の関係上、例年より1月遅れでの実施となった。玉利和弘緑風会会長、原田勇学園長のご挨拶で開会した。講話では、「酪農学園の現状と課題」と題して小野寺秀一教授(入試部長)より入試を取り巻く厳しい現状報告が行われた。
研修1では「積雪寒冷地における葉菜類の周年栽培を実現する省力的な管理技術の検討」と題して北海道帯広農業高等学校 飛谷淳一教諭から十勝地域においてのホウレンソウとコマツナの年8作の周年栽培と省力的な栽培管理技術について実践報告していただいた。
研修2は技術研修講座として「身近になってしまった放射線を正しく知る」と題して、本学獣医学群 遠藤大二教授より目に見えない放射線の影響や測定方法について、危険の無い範囲での環境中の放射線を測定する講義・実習を行った。
19時より会場を野幌町「あおい」に移し、約40名の出席者により懇談会が開催された。本学からは原田学園長、干場信司農食環境学群長はじめ酪農学部各学科長、入試部、就職部関係者のご出席をいただいた。同窓会連合会からは野村武会長、浦川が出席した。岡田副会長の進行により出席者全員が紹介され、なごやかな懇談の場を持つことが出来た。