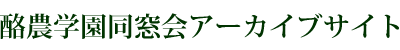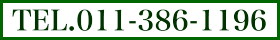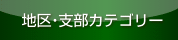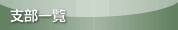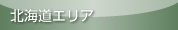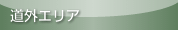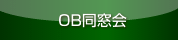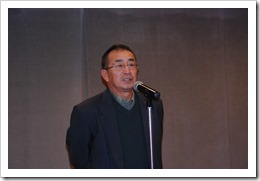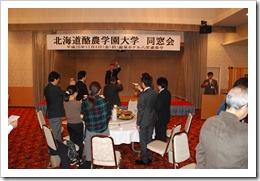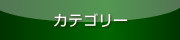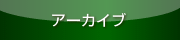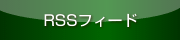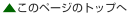支部新着情報一覧
富山県支部総会・懇親会の概要
富山県支部は、平成28年10月16日(日) 午後2時から総会(約30分間)、集合写真撮影、懇親会(午後5時頃)を持ちました。この会には、先立って持たれた中部地区各県支部長会議に参加された小山久一同窓会会長、谷山弘行学園理事長、近雅宣学園常務理事のお3方が来賓として参加してくださいました。
富山県支部の会員は事務局からの名簿では約140名(重複を除く)が登録されていましたが、事務局名簿に従い富山県支部総会の開催案内を発送したところ2通のみが宛先不明でした。総会等案内の返信数は74通(回収率約53%)、内出席者数29名(21%)、欠席者数45名(32%)でした。欠席と案内された会員の中には県外に在住のため出席を見合わせたい(横浜市在住の方は名前が空欄)という方が 6名ありました。
総会の議題は会則の改正が主でしたが、賛成多数で承認され、役員も再任となって総会も閉じられ、写真撮影室にて富山県支部2016年度総会の記念集合写真を撮り、待望の懇親会となりました。
懇親会は、谷山学園理事長の挨拶、近雅宣常務理事の乾杯に始まり、宴の中で小山久一同窓会会長が黒澤酉蔵翁の踏跡についてプロジェクターを活用して独自に調査された内容を丁寧に報告されました。
会員の皆様は、最初は紳士淑女の様相を呈していましたが、宴も進み、お酒も十分に体に行き届き、会員の心が豊かな状況になってきたころから「野幌原始人」の叫び声が大嵐となって吹きはじめました。中身はそれぞれの思い出話とかで話の花が咲き、大きな笑い声、大きな話声がそこここでわき上がって会場を埋め尽くし、小山会長がマイクを通して語られる酉蔵翁についての説明も聞き取れなくなるくらいに活気に溢れる和気あいあいの会となりました。「野幌原始人気質」つまり、酪農学園気質は、どんなに年を経ても卒業生の心からはなくならないものであるといたく感じいりました。時は早いもの、午後五時を過ぎ、全員が輪になって酪農賛歌を大声で歌い、泉澤ひとみ副会長の乾杯で会を結びました。
総会と懇親会の進行は石川憲明副会長により取り仕切られ、司会は、富山県支部の会計担当で新進気鋭の中村(早苗)美智子姉が進めました。中村姉の司会はとても可愛くて優しく、老若男女を包み込む包容力があり、野幌原始人の方々は心を癒していただけたようで、来賓の方々からも好評でした。
会の会員層は、機農高校、三愛高校、短期大学、四年制大学、六年制大学、大学院等を2015年度までに卒業、修了された方々という多年代層( 60年超)によって構成されていますが、野幌の大自然の中で培われた三愛精神と実学教育という心の豊かさは、脈々と今も継続されていると感じた有益な時でした。
今回の2016年度総会等の開催は、酪農学園同窓会が統合されて初めての会であったことから、短期大学を昭和33年に卒業された女性から「短期大学を卒業した私でも参加して良いのでしょうか。富山県に来て20数年、始めて同窓会の案内をいただいたのです。宮城県に住む同じ学寮に居た方も私と同じで、一度も宮城県支部の同窓会開催案内をいただいていないといっているし・・・・・。」という問い合わせがありました。その方には「高校、短大、大学、大学院を卒業・修了した人が所属する各々の同窓会は、昨年に統合され一本化されましたので酪農学園を卒業・修了された方の全てが各地区各支部の会員となっています。ですから、会員の方はどなたでも参加できますし、ご参加をお願いしたいと思います」とご案内したところ慶んで出席をしてくださいました。また、機農高校卒業後、酪農学科を昭和42年に卒業された男性は、自社で熟成された吟醸酒数本を持参され、会員の皆さんに振る舞われましたが、その味はとても美味で譬え様のない麗しい味がしました。
同窓会の総会等へは、若い年代の出席が少ない傾向にありますが、今回、2003年に卒業された方や比較的若い会員が出て下さり、世話人として会の運営に力を注いで下さったので深く感謝した次第です。(文責:富山県支部長 永井 勝)
中部地区各県支部長会議の概要
 会議は平成28年10月16日、富山県都の富山市に所在するホテル グランテラス冨山で午後1時30分から約30分間の予定で開かれた。来賓は同窓会の小山久一会長、学園の谷山弘行理事長、近雅宣常務理事、中部地区各県支部長の加藤正木氏(愛知県)、村田耕一郎氏(三重県)、岩佐達男氏(岐阜県)、藤井敏夫氏(石川県)、永井勝(富山県、地区長)の8名が参集したが、欠席支部は藤村宗道氏(静岡県)と仲村和典氏(福井県)の2名であった。
会議は平成28年10月16日、富山県都の富山市に所在するホテル グランテラス冨山で午後1時30分から約30分間の予定で開かれた。来賓は同窓会の小山久一会長、学園の谷山弘行理事長、近雅宣常務理事、中部地区各県支部長の加藤正木氏(愛知県)、村田耕一郎氏(三重県)、岩佐達男氏(岐阜県)、藤井敏夫氏(石川県)、永井勝(富山県、地区長)の8名が参集したが、欠席支部は藤村宗道氏(静岡県)と仲村和典氏(福井県)の2名であった。
議事は、地区長および来賓の挨拶、各県地区長の紹介の後に本題の各県支部活動概要が報告された。
愛知県:6月19日(日)、来賓に同窓会は堀内信良副会長、学園は福山二仁常務理事、竹花一成学、安宅一夫名誉教授を招き50余名で総会、懇親会を開いた。三重県:特別な活動がないが地区長が愛知県支部の総会に加わり愛知県会員と情報交換を行った。
岐阜県:10月15日(土)、来賓に同窓会の小山久一会長、学園の谷山弘行理事長、近雅宣常務理事を招き15名で総会、懇親会を開いた。
石川県:支部活動はないが、獣医学科同窓会員は平成29年2月に金沢市で獣医学術学会年次大会が開催されるために会員が集まり協力体勢をつくるための打合会を持った。
静岡県:新しい藤村支部長代理の下、11月26日(土)~27日(日)に総会と懇親会を開く予定である。
福井県:支部活動状況は特段にないが近い将来に総会と懇親会を開くべく勘案中である。
富山県:本日10月16日(日)の午後2時から5時にかけ来賓に同窓会の小山久一会長、学園の谷山弘行理事長、近雅宣常務理事を招き29名が参集して総会、懇親会を開いた。
等の報告の後、同窓会職域OB会・酪小獣・地塩会(小動物臨床医研究会・中部地区)の設立と活動報告等の概況報告がなされた。酪小獣は全国の各ブロックに所在する学園出身小動物臨床医が大学との縦の繋がり、地区の会員相互の横の繋がりを緊密にして学術の研鑽と協力体制を強め、相互に発展する目的で各ブロックに結成する努力がなされた。
各会は札幌が麦の会、関東が白樺会、中部が地塩会、関西、九州、四国、東北の各ブロックに会の結成がなされた。酪小獣・地塩会は2012年に発足、2016年(H28年)10月30日に第5回の総会、研究会がもたれた。会長は地区長の永井勝、事務局長は愛知県支部長の加藤正木氏、副会長3名並びに各県幹事18名、会員は約100名で組織されている。研究会の講師は毎年、大学獣医学科が派遣してくださる先生方によってなされ、実践的で具体的な新たな技術や理論を学ぶ場となっている。
以上の報告と質疑応答は、富山県支部総会の開催時間にまで食い込んだため、議事の了承がなされて会議が閉じられた。(文責 地区長 永井 勝)
近畿地区総会・懇親会報告
10月1日午前10時から京都聖護院御殿荘を会場に近畿地区総会・懇親会が開催された。出席者は地区会員13名、本学から加藤清雄同窓副会長、谷山弘行理事長、近雅宣常務理事にご出席いただきました。
総会は山本浩光地区会長の挨拶に続き、近畿地区、悲願の関西事務所の設立について、現状等を、向井京都支部長より説明が有りました。その後、現状における意見、取り組みを進めるにあたっての意見、今後の進め方等についての意見を参加者より聞いた。具体的な意見が数々提案された。
今後の進め方として、これらの意見を十分考慮しつつ、近畿地区の中に、関西事務所の設置にむけての委員会を立ち上げた。
委員として、山本近畿地区長・向井京都支部長・澤竹和歌山支部長・河野緑風会近畿支部長の4名を選出した。このメンバーにて同窓会、学校と設置に向けての協議をしていく以上の事を決めました。
1時からの懇親会の部
加藤同窓会副会長、谷山理事長、近常務理事のご挨拶をいただき、和やかで、有意義な懇親会となりました。 (文責 山本浩光)
北海道第3(道南)地区同窓会報告
11月5日(土)に開催された酪農学園大学主催の「第51回酪農公開講座」の前日の4日午後6時から、「八雲遊楽亭」を会場にして、酪農学園同窓会道南地区同窓会が開催された
同総会には八雲町周辺の同窓生、および大学関係者等28名が出席した。本学からは竹花一成学長や講師の小岩政照教授、エクステンションセンター関係者、同総会等から6名が出席した。
会は荻本正八雲町役場課長補佐(短大ⅡコースOB)の司会進行で進められ、開会挨拶を道南地区会長都築信夫氏が歓迎の挨拶と同窓の絆の重要性を述べた。
続いて来賓挨拶として竹花一成学長から公開講座開催に伴う関係者へのお礼と大学の現況等について、ご紹介いただいた。
次に今回の開催地の中心である八雲町、森町、長万部町で構成される渡島第二支部の吉田英明支部長の乾杯により懇親会となった。
その後、出席者が一人ずつ壇上にあがり、自己紹介と近況報告を行なった。小岩教授(講師)は北海道酪農発祥の地とも言える八雲町での公開講座の講師としての抱負を述べた。機農高校OB加藤喜一氏からは「酪農学園八雲会」という酪農学園同窓会が以前に活動していた貴重なお話しをご紹介いただいた。
最後は加藤氏の万歳三唱により会を閉じたが、時間切れで集合写真撮影の後、酪農讃歌合唱が出来なかったことが心残りでした。
今回の同窓会は八雲町周辺にお住いの高校(機農・三愛女子)、短大、大学各学科の同窓生22名に出席いただき、今年就職したOB(H27卒)から機農高校農業科11期OB(S29卒)まで幅広い年齢層の同窓生にご参加いただきました。
なお、5日(土)に開催された第51回酪農公開講座は90名を超える出席者があり、盛会裏に終了したとのことでした。
中部地区岐阜県支部総会報告
10月15日午後7時からホテルグランヴェール岐山を会場に総会・懇親会が開催された。出席者は支部会員15名、本学から小山久一同窓会長、谷山弘行理事長、近雅宣常務理事にご出席いただきました。
総会は岩佐達男支部長の挨拶に続き、小山同窓会長、谷山理事長のご挨拶をいただきました。議事に入り、まず支部規約、さらに役員が承認されました。
さらに今後の活動方針として、県内を5地区に分け、それぞれの地区長を配してその地区を取りまとめていただくことになりました。
そして、岐阜県は広いので、各地区を持ち回りで同窓会を開催することが提案されました。
引き続き記念撮影の後、近常務理事の乾杯の音頭により懇親会に入りました。全員の自己紹介をして、おおいに親睦を深めることができました。
渡辺峯雄会員の中締めの後、恒例の酪農賛歌を全員で円陣を組んで斉唱し散会となりました。(文責 岐阜県支部長 岩佐達男)
福山二仁様のご苦労さん会開催報告
酪農学園同窓会
関東甲信越地区東京都支部
9月26日に関東甲信越地区と東京都支部は共催にて、福山二仁前常務理事(獣医3期 関東甲信越地区並びに東京都支部理事)のご苦労さん会を開催しましたのでご報告いたします。
 第1部として東京オフィスにてセレモニーを開催しました。須田利明東京都支部長の司会で、最初に本会を代表して岡田会長から、福山さんは2009年から学園の改革に尽力され、常務理事として学園に企業経営感覚で運営に努力し、学園経営を黒字体質に変える一助に貢献しまたと紹介がありました。続いて野田修平顧問(元会長)から心にしみるねぎらいの言葉と学園に招かれた時の経過の話がありました。次に高澤靖所長からは、東京オフィスを一等地に移設した功績をたたえる話が紹介されました。
第1部として東京オフィスにてセレモニーを開催しました。須田利明東京都支部長の司会で、最初に本会を代表して岡田会長から、福山さんは2009年から学園の改革に尽力され、常務理事として学園に企業経営感覚で運営に努力し、学園経営を黒字体質に変える一助に貢献しまたと紹介がありました。続いて野田修平顧問(元会長)から心にしみるねぎらいの言葉と学園に招かれた時の経過の話がありました。次に高澤靖所長からは、東京オフィスを一等地に移設した功績をたたえる話が紹介されました。
福山さんからは、常務理事となった経緯と、学園改革への取り組みの話がありました。6年間常務理事として企業経営感覚を取り入れ幾多の改革を行って、赤字経営から黒字体質に変えることができたとの報告がありました。
 第2部は、東京オフィスのあるビルの最上階にある回転レストラン「銀座スカイラウンジ」にて慰労のパーティを開きました。有楽町を中心とした360度の薄暮・夜景を見ながらの楽しい懇談のひと時を過ごしました。(文責 事務局 渡会福次郎)
第2部は、東京オフィスのあるビルの最上階にある回転レストラン「銀座スカイラウンジ」にて慰労のパーティを開きました。有楽町を中心とした360度の薄暮・夜景を見ながらの楽しい懇談のひと時を過ごしました。(文責 事務局 渡会福次郎)
酪農学園同窓会兵庫支部第3回総会・懇親会報告

去る9月11日(日)13時30からパレス神戸を会場にして第3回となる兵庫県支部総会が開催されました。支部会員は39名が出席。大学同窓会から小山久一会長、石下真人教授(講師)、近畿地区から山本浩光支部長、清水顧問、各府県支部長(4名)に花を添えていただき、終始和やかで大変盛り上がりました。
 総会は議長(池内俊久氏)によりスムーズに進行し、議題として①平成27年度事業報告、②平成27年度会計・監査報告、③平成28.29年度役員の承認、④平成28年度事業計画の審議が行われた。
総会は議長(池内俊久氏)によりスムーズに進行し、議題として①平成27年度事業報告、②平成27年度会計・監査報告、③平成28.29年度役員の承認、④平成28年度事業計画の審議が行われた。
小河支部長のご挨拶の中で、台風10号被害についてふれ、集まった義援金54,570円は小山会長に預けることになった。
 講演では本学肉製品製造学研究室 石下真人教授から食肉製品の製造、安全性、表示、安全安心な食品等について、分かり易く説明していただきました。また、小山久一同窓会長による講話では黒澤酉蔵先生の歴史について説明されました。
講演では本学肉製品製造学研究室 石下真人教授から食肉製品の製造、安全性、表示、安全安心な食品等について、分かり易く説明していただきました。また、小山久一同窓会長による講話では黒澤酉蔵先生の歴史について説明されました。
記念撮影ののち、懇親会が開催され、小河支部長の挨拶、小山同窓会長の祝辞につづいて山本近畿支部長の乾杯のご発声で始まりました。
 一人ずつ全員が自己紹介、最後は酪農讃歌を肩組んで合唱、伊南副支部長の一本締めでお開きとなりました。 (文責 事務局長 河野雅晴)
一人ずつ全員が自己紹介、最後は酪農讃歌を肩組んで合唱、伊南副支部長の一本締めでお開きとなりました。 (文責 事務局長 河野雅晴)
雄武町デーリィクラブ交流会報告
近年の北海道酪農情勢及びOBと委託実習生との親睦会
例年、本町同窓会(雄武町デーリィクラブ会長 細川登久市)が主催し、本学学生委託実習の学生諸君の労をねぎらうのが主旨で開催しています。
今年度は去る平成28年9月2日(金) 午後8時から雄武町内の「出塚食品」2階を会場して恒例の委託実習生を囲んでの親睦会が開催された。当初予定数は20名であったが所用が重なり、 最終参加者数16名となった。
 なによりも委託実習を経験した者同士、委託実習の今昔を語らいながら、学生諸君からも実習の感想など、本人の将来の展望なども語ってもらい我々もそれにじっと耳を傾けていた。
なによりも委託実習を経験した者同士、委託実習の今昔を語らいながら、学生諸君からも実習の感想など、本人の将来の展望なども語ってもらい我々もそれにじっと耳を傾けていた。
現在の学生委託実習は必須から選択科目に変更になって数年経過しましたが、従来の必須の時代からは学生諸君の実習に対しての取り組みにはとても真剣さが伝わります。
とくに委託実習の体験を教訓に将来の就職先への展望を見据えているのが肌で感じます。学生諸君と例年開催している親睦会も飲食を共にしながら時間を忘れ親睦を深めさせてもらいました。 なお、例年同窓会様より助成金を賜ります事、厚くお礼申し上げます。
(文責:雄武町デーリィクラブ事務局 竹田浩二)
京都府支部・滋賀県支部合同懇親会報告
「京都府支部・滋賀県支部合同懇親会」を8月20日に行いました。
 今回は出席・返信共に悪く、会運営の危機を感じる結果となりました。そのこともあり、今後の運営についての話題が話の中心になりました。
今回は出席・返信共に悪く、会運営の危機を感じる結果となりました。そのこともあり、今後の運営についての話題が話の中心になりました。
山本近畿支部長や青木滋賀支部長も参加しており、京都支部のみの運営ではなく近畿地域での盛り上げ方が討論されました。これまでも参加者の年齢が高いことが問題となっており、若・中年層の参加を進めることが活性化には重要だと言うことを再確認しました。
 彼らの参加を増やすためには、交流を通じたネットワークの構築だけでなく実利のある運営が求められていると感じました。
彼らの参加を増やすためには、交流を通じたネットワークの構築だけでなく実利のある運営が求められていると感じました。
今後は、各自の生産物や活動の紹介が出来、それを一般の方にも広く紹介していけるような組織になるという目標を作り終了しました。 (文責 京都支部事務局長 佐藤豪三)
第9回酪農学園同窓会兵庫支部役員会報告
第9回となる兵庫県支部役員会が8月7日、役員9名の出席により開催された。小河支部長不在の為、開会のご挨拶が伊南晋一副支部長から行なわれ、「今日の作業を慎重に且つ迅速にお願いします。」と述べた。
 本日の役員会の内容は案内・昨年度報告・返信用はがきの袋詰め作業(約700人分)作業別に分担を決めて行う。・事務局の名称・住所明記のスタンプの押印・封筒へのタックシール貼り付け・案内文・昨年総会の報告文の折り込み・封筒への袋詰めを行なった。昨年度4人で6時間かかった作業が2時間半で終了する。
本日の役員会の内容は案内・昨年度報告・返信用はがきの袋詰め作業(約700人分)作業別に分担を決めて行う。・事務局の名称・住所明記のスタンプの押印・封筒へのタックシール貼り付け・案内文・昨年総会の報告文の折り込み・封筒への袋詰めを行なった。昨年度4人で6時間かかった作業が2時間半で終了する。
その後、別紙の実施要領により総会当日の役割分担の確認を実施した。次に会計と監査により会計監査会を実施した。その他について、次回9月4日(日)11時から参加状況の把握と呼びかけ依頼、当日の役割分担の確認等を行なうこととした。 最後に閉会の挨拶が山取洋彦副支部長より行なわれ、「お疲れ様でした。総会に向けてみなさんのより一層のご協力をお願いします。」と述べられた。(文責 事務局長 河野雅晴)