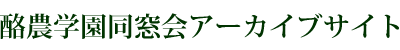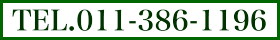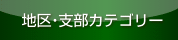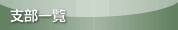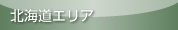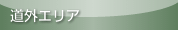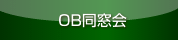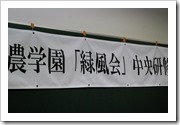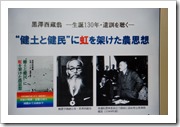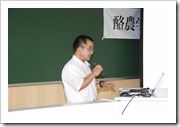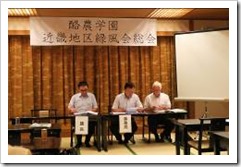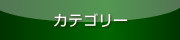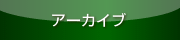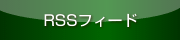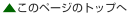OB会新着情報一覧
緑風会兵庫支部第5回総会兼親睦会報告
緑風会兵庫支部第5回総会兼親睦会報告
 8月1日(土)、東加古川寿司店にて緑風会兵庫支部第5回総会兼親睦会を開催しました。今年は、12名の出席でした。改まった総会ではなく、親睦会を兼ねた気楽な会にしようということになりました。
8月1日(土)、東加古川寿司店にて緑風会兵庫支部第5回総会兼親睦会を開催しました。今年は、12名の出席でした。改まった総会ではなく、親睦会を兼ねた気楽な会にしようということになりました。
6月28日の緑風会近畿地区第2回総会の報告、11月15日にパレス神戸で開催予定の同窓会兵庫支部第2回総会の案内及び出席依頼、大学の入試状況と進路指導のお願いを私が行いました。
親睦会では、全員の現況報告に耳を傾け、終始アットホームな雰囲気で進行していきました。気がつけば4時間が経っていました。(文責 兵庫支部顧問 河野雅晴)
第8回酪農学園「緑風会」中央研修会報告
第8回酪農学園「緑風会」中央研修会報告
例年以上の猛暑が続く8月1日(土)午後1時から第8回を数える緑風会(教員OB会)の中央研修会がC1号館101教室を会場に、学園関係者を含めて34名の出席により開催された。岡田正裕事務局長の司会で進行。開会式では主催者代表挨拶として西田丈夫会長(岩見沢農業高校校長)から本日の教育実践報告でもあるSSH(Super Science HigtSchool)やAFSの紹介や干場敏博事務局長の退任報告があり、謝意を述べた。
共催者代表挨拶では寺脇良悟教職センター長から日頃の教育実習等へのお礼と講演2の教職コースについて紹介した。同窓会と入試部からは配付資料の紹介と同窓会の概要報告並びに小山久一同窓会会長から同窓会の現況についてご紹介いただいた。
2.講演Ⅰでは仙北富志和学園長から「黒澤酉蔵の農思想に学ぶ」と題して約50分、黒澤酉蔵翁生誕130年・遺訓を聴く「健土と健民に虹を架けた農思想」のスライドを用いて、黒澤翁の生い立ちから時系列的に主な遺訓集から抜粋した翁の農思想を紹介した。
学園長は、産業界、教育界、政界等で幅広く活動した翁は3回叙勲を受けたことや、今日国土が放射能で汚染され、自給率が低下する中で、健土健民健産の三健論を唱えた翁の先見性を紹介し、亡国論への警鐘を鳴らした。
3.教育実践発表では(1)SSH(Super Science Highschool)への取組、完成年度を迎えてと題して北海道岩見沢農業高等学校 松浦直哉教諭が発表した。
SSHとは「将来国際的に活躍し得る科学技術系人材の育成」を目的とした文部科学省が指定する国家プロジェクトであり、指定校が203校、内農業高校6校、道内高校10校となっており、指定期間は5カ年となっている。H25年に指定された岩見沢農業高校は「我が国の農業科学技術系人材を育成する農業科学プログラムの開発」をめざし、「農業と科学および英語教育を融合した学習プログラム」について、目指すものとして1)農業科学技術を高める。2)課題解決能力や論理的思考力を高める。3)世界の貢献できる国際性を身につける。将来像として農業・科学技術のスペシャリストや農業・理工系大学への進学となっている。
主な事業内容として7時間目の設定や土曜授業、ALTの常駐、海外研修、学会発表等が挙げられる。まとめとして英語への親近感等が紹介された。
続いて(2)北海道農業高等学校実習生産品の安全管理「自主規制制度AFS」への取組と題して同じく岩見沢農業高等学校渡部哲哉教諭から報告いただいた。
事例として昨年発生した「ローストチキンの過熱不足による製品の回収」の事故発生での保健所とのやり取りを契機に農業高校での実習生産品の販売にあたり自主規制制度認証制度を発足した。製造許可書の確認、製造施設の整理整頓・環境整備、製造者の体調確認等を行い、認証制度への商品登録申請を行い、PRシート、製造許可確認表、製造工程表を認証委員会に提出することになっている。イベント出品への認証シール貼付が義務付けられる場合もある。
3.講演Ⅱとして「本学教員養成の取組-教職コースの現状」を教職課程室長の岡島毅教授(草地・畜産学教育研究室)から本学の教職コースの概要について詳細にご紹介いただいた。
研修会終了後は、会場をレストトラン「トンデン館」に移動して懇談会が開催された。
第四回酪小獣麦の会 総会・研修会開催報告
第四回酪小獣麦の会 総会・研修会開催報告

 平成27年7月26日(日)酪農学園大学附属動物病院2階大会議室において、酪小獣麦の会総会・研修会が35名の出席のもと午後3時より開催されました。 まず研修会に先立ち、山下附属動物病院長による病院の現状と増床計画および研修会講師の紹介などをスライドを使って説明を頂きました。
平成27年7月26日(日)酪農学園大学附属動物病院2階大会議室において、酪小獣麦の会総会・研修会が35名の出席のもと午後3時より開催されました。 まず研修会に先立ち、山下附属動物病院長による病院の現状と増床計画および研修会講師の紹介などをスライドを使って説明を頂きました。
研修会は、井坂光宏准教授(伴侶動物医療学)による「これまでの臨床医としての経験と肺高血圧症について」、嶋本良則教授(獣医保健看護学類)による「これまでの研究と今後の研究-臨床応用を目指して」というテーマで約1時間ずつ講演をしていただきました。
総会は午後5時より松尾直樹事務局長の進行で始められ、南 繁会長の会長あいさつ、野村 武前酪農学園同窓会連合会会長および中出哲也獣医学類長のあいさつと続きました。
総会議長には札幌市開業の林 茂先生が選出され林議長進行のもとで議事進行が進められました。
議案は、①平成26年度事業報告と決算報告について報告があり、星野佐登志監事による会計監査報告がありました。続いて②平成26年度剰余金処分案③平成27年度事業計画案と収支予算案④平成27年度会費の金額および徴収方法について審議され、承認されました。
また、体調不良で副会長を辞任された北島哲也氏の後任には、役員会で推薦を受けた玉井 聡氏が承認を受け副会長に就任しました。
規約改正についての議事の場面では、他大学卒業生は賛助会員としての入会を認め、それに関わる会則の変更がありました。さらに会員区分をより明確化したほうがよいのではないかという廉澤 剛教授からの提言があり、今後役員会で検討していくこととなりました。
総会研修会のあとには、トンデンファームに会場を移し懇親会を開催しました。
まず、副会長に就任した玉井 聡氏の就任あいさつと乾杯の音頭により和やかな雰囲気で懇親会は進み、途中からは例年の通り全員がマイクの前に立ち、自己紹介を含めた近況報告や考えを述べ大変盛り上がりました。最後は、中出先生による酪農讃歌では全員で肩を組み合唱し閉会となりました。(文責 事務局 松尾直樹)
五寮会(機農高校希望寮OB会)開催報告
五寮会(機農高校希望寮OB会)開催報告

去る7月18日(土)正午から夕刻まで江別市大麻新町の野みつ子宅および金寿司において出席者29名のより五寮会が開催された。代表幹事は三分一正記氏。
今回の五寮会(野幌機農高等学校の故野喜一郎が寮監であった第五寮(希望寮)卒業生の会)の出席者は、昭和21年~32年卒業までの同窓生26名と本学関係者3名。
まず野喜一郎夫人宅に集合し、野夫人に面会後、近隣の金寿司で懇親会を行った。
会は三分一氏の進行のもとに、学園同窓会の動向の説明と大谷俊昭氏の挨拶ののちに懇親会が開催された。高校卒業60~70年経過しているとは思えぬ記憶力とパワーが感じられた。また、将来の学園について多くの期待の思いが伝えられた。(文責 野 英二)

短大五期生の集いの報告
短大五期生の集いの報告

平成4年、樋浦学長の一周忌を機に、札幌で集まって以来14回目、去る7月6~7日、大滝の第ニ名水亭に13名が集う。
最盛期は40数名も参加したが、往時の活力溢れる学友も八十路に入り、22名が他界し、足腰の痛みや体調不良などで年々参加者も減る。これも人生の無常、自然の流れというべきか。
この間、金沢や群馬など本州で5回、北海道で9回、先生方をご招待しての研修もしたが、すでに鬼籍に入った師も多く寂しくなった。
しかし、顔を合わせると忽ち60余年前に戻り、樋浦組の労作、特色ある諸先生の講義、きびしい食生活やアルバイトなど苦楽を共にしたなつかしい話題は尽きることがない。
今後も可能な限りこの会を継続させ、お互いの絆と友情を深めたい。この間、学園同窓会には大変ご支援を頂き、学友一同心から感謝してご報告にかえます。(金田孝次記)
酪農学園近畿地区緑風会第2回総会報告
酪農学園近畿地区緑風会第2回総会報告
平成27年6月28日(日)10時30分から午後2時30分まで神戸市パレス神戸を会場に行われた。出席者は15名。本学からは福山二仁常務理事、干場信司学長、岩森昭憲課長補佐。同窓会から小山久一会長、近畿地区山本浩光会長が出席した。
1.大学の説明並びに質疑応答について、干場学長より大学概要説明ののち岩森入試課課長補佐より入試説明が行われた。特に獣医保健看護学類、獣医学類、教職コース、管理栄養士コースの詳しい説明があり、参加会員から本年度教員採用者のデータについて、現役採用だけでなく、臨時講師からの採用者も加えて欲しいとの要望や臨時講師の採用に緑風会を活用して欲しい等の意見が出された。
2.総会では平成26年度事業・会計報告、監査報告が行われた。また平成27・28年度事業計画が審議され、承認された。平成28年度総会は6月28日の予定。
記念撮影ののち懇親会が開催された。
福山常務の祝辞に次ぐ小山会長の乾杯の発声で懇親会が開始され、終始和やかな雰囲気で大変盛り上がり出席者全員によるスピーチが行われた。大学時代の思い出話や大学や緑風会への思い、近況等がユーモラスに話された。同じ酪農学園大学の同窓生としてより団結が強まる懇親会となった。最後は肩を組んで酪農讃歌を熱唱、澤竹副会長の閉会の挨拶でお開きとなった。(文責 河野雅晴)
2015準会員(学生)応援企画メニュー終了!
2015準会員(学生)応援企画メニュー終了!
準会員応援企画メニューは大学生協の協力により、6月2日(火)から4回にわたり、日替わり丼の形式で行われた。すべて酪農牛乳付で200円の特別価格。
2日:かき揚げ天丼。10日(水):ミートソースハンバーグ丼。18日(木):チキンカツ玉丼。26日(金)の最終日はハヤシソースメンチカツ丼。
午前10時~午後2時の間で、各日250食の計1000食が用意されたが、各日ともにお昼近くで完売となった。
アンケートからは食欲旺盛な学生からのパワー丼復活等の希望等も寄せられた。
好評につき次年度も多分企画すると思いますが皆様のご意見を同窓会までお寄せいただければ幸いです。
4日間の様子を写真でお送りします。
6月02日
6月10日
6月18日
6月26日
林家卯三郎氏(獣医学科25期)後援会発足のお知らせ
林家卯三郎氏(獣医学科25期小川祐之介氏)後援会発足のお知らせ

岐阜県羽島市在住で元岐阜県支部長岩佐達男氏(獣医学科8期)よりのお手紙を紹介します。
以前に卯三郎さんが故郷の岐阜県笠松町で落語会を催したいと言っていたため、町役場に出向いて話をしてみたら、トントン拍子で2月28日に笠松町で落語会が実現しました。
その後、後援会の話が持ち上がり、下記の安藤さんを会長に立ち上がりました。~中略~卯三郎さんの強力な後押しが出来ましたのでお知らせします。なお羽島の後援会なので入会するのはお任せします。
<概要>
落語家・林家卯三郎(はやしやうさぶろう)の後援会へのご入会をお待ちしております。
下記リンクより必ず後援会規約をご一読の上、内容をご承諾いただいた上でご入会ください。
・後援会規約
■林家卯三郎(はやしやうさぶろう)後援会事務局/安藤 功
■事務局/〒501-6330 岐阜県羽島市堀津町2151(デジックスアンドリンク株式会社内)
■TEL/058-397-0565 FAX/058-397-0564 MAIL/ando5108@gmail.com
【目的】
私たちは落語家を純粋に愛し、世の中を幸せにしてくれる林家卯三郎を応援するために活動します。
各地での定期公演には、皆様のご協力が必要ですので、ご賛同いただける方は何卒よろしくお願いします。
【主な活動】
(1)会員の方には会報誌『林家卯三郎通信』をお送りいたします。
(2)公演の情報をメールにてお届けします。(ホームページでも更新していきます)
(写真・記事は公式HPから転載)
後援会に関する卯三郎公式HPはこちらからご覧下さい ⇒http://usaburo.net/
機農寮お別れと感謝の集いを開催
機農寮お別れと感謝の集いを開催
とわの森三愛高校の男子寮「機農寮」は、今年3月31日をもって閉寮となり、44年の歴史を閉じました。この寮を巣立っていった同窓生にとっては、かけがえのない青春時代を過ごした寮です。かつての寮生などが6月6日にお別れの集いを企画し、元寮生、元教職員、高校教員、3月まで機農寮で過ごした高校生など130名が、記念礼拝と懇談会に出席しました。

記念礼拝では、榮忍校長が、聖書のマタイによる福音書の、イエスが自分のところに連れて来られた中風の人を治す奇跡の物語を紹介し、「イエスは、中風の人を何とかしたいと思った仲間たちの気持ちを受け止めて、中風の人の罪を許して癒したというのが真実です。仲間がいてよかったと思い、心がつながるのが寮です。卒業しても、仲間がいて、支えあって困窮を乗り越えてきたことを思い出して、人生に立ち向かってください。機農寮の役割が終わり、希望寮に引き継がれます。受け継ぐべきものは何か、考えてください」と奨励をしました。

続いて、お別れと感謝の集いを企画した浅野政輝実行委員長が、「機農寮は44年の歴史を閉じましたが、ぜひ、先生や卒業生の方々と寮の思い出を共有したいと思い、集いを開催しました」とあいさつしました。

次に、仙北富志和学園長が、「黒澤酉蔵先生から、「機農とは人生の教えで、人生においてチャンスを逃すな」と言われました。また、「チャンスのタイミングを掴むためには、準備と努力と希望が必要」と教えられました。機農は学園の精神の原点です。この精神はなくしてはならないと思います」と祝辞を述べました。
また、酪農学園同窓会連合会の野村武顧問が、「酪農学園の卒業生が15万人を超えました。黒澤酉蔵先生は、農業者を養成するため、実学教育を行う機農高校を作りました。酪農 家になって活躍する同窓生が全国にたくさんいます。これからも機農の精神を引き継いでいってください」と祝辞を述べました。
家になって活躍する同窓生が全国にたくさんいます。これからも機農の精神を引き継いでいってください」と祝辞を述べました。

続いて、希望寮寮長の齊藤丈嗣さん(3年)が、「機農寮で2年間過ごしました。不便なこともあったけれども、思い出がたくさんあります。希望寮に建物が変わっても、寮の先輩、後輩の絆を作っていきたい」とあいさつしました。
記念礼拝の終了後、全員で寮の前で記念撮影し、その後、食堂に移動して懇談会が行われました。(酪農学園公式HPより転載)
原田勇先生遺稿・追悼集が出版されました、
このたび酪農学園大学土壌植物栄養学研究室同窓会の原田勇先生遺稿・追悼集編集委員による
原田勇先生遺稿・追悼集『酪農そして世界平和への想い-酪農学園とともに歩んだ人生―』
が出版されました。
2012年12月16日にご逝去された原田勇前学園長の遺稿・追悼集を編纂したものです。
装丁はハードカバーで469P22cm 非売品 北海道リハビリ出版。
本書は、原田先生が遺した遺稿集の中から、編集委員会の責任で取捨選択し、年代順に収録したものと、皆様からの追悼メッセージを収録したものです。表紙は右記のとおりです。