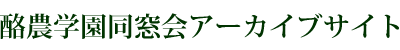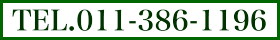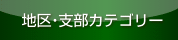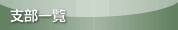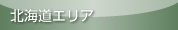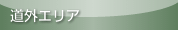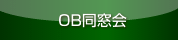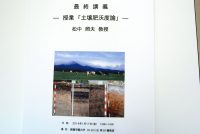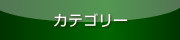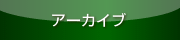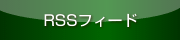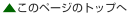OB会新着情報一覧
農業経済学科’93年度入学生TPP情報交換会開催報告
農業経済学科‘93年度入学生TPP情報交換会開催報告

2月22日(土)18時~23時、札幌エルプラザ:札幌市環境プラザにおいて参加者12名で標記の情報交換会が開催された。
TPP交渉が官僚交渉となり、いつ妥結するかわからない中、「反対一辺倒ではなく、経済学的に学びたい」という卒業生たちの想いでこの情報交換会を実施しました。
参加者で簡単な自己紹介の後、小糸准教授から『TPP締結直前に考える貿易交渉の現状と北海道の農業環境』を講義していただきました。
非常にお忙しい中、様々な視点から資料を提示していただき、自由化・経済の開放にすすむことは経済学的には自然の流れであるが、アメリカなども市場開放に否定的な部分もあることなどをお話いただきました。
その後質疑応答や懇親会を通じ、さらなる情報交換を行うことができ、今後もこのような機会を年1回程度行っていくことになりました。 (文責 松本卓也)
2013年度酪進会開催報告
2013年度酪進会開催報告
2013年度酪進会定例会(酪農学科 家畜管理・行動学研究室同窓会)を2013年2月15日(土),札幌にて開催しました。西埜先生は残念ながら御欠席でしたが,干場教授・森田教授・道内OB・OGに加え,51期となる卒業年度のゼミ学生を迎え総勢約44名の出席でした。その他,ご都合がつかず参加されなかったOB・OGの皆様方から卒業生へ多くのメッセージをいただいております。
今年度の研究室の活動報告を干場教授,森田教授からいただいた後に,日頃の研究成果のご報告を兼ねた研修会として,大学院生からの発表を行いました。内容は『酪農家で働く女性の満足度低下要因~十勝地方S町における乳牛の健康状態が満足度に及ぼす影響~』についてでした。現場に即した内容で,現状を裏付ける報告となり,発表者・参加者ともに有意義な時間となりました。
後半は,新しく酪進会会員となる新卒業生の歓迎会が行われました。大学の新卒業生からは卒業論文のご報告,卒業後の進路,抱負が発表され,OB・OGの方々からもそれぞれ近況報告や今後の抱負,新卒業生に対する励ましの言葉が述べられました。
本年度の酪進会も盛大に開催され,先生方,OB・OGの方々や新卒業生とのすばらしい一時を過ごすことができました。これからも幅広い世代が集う場として酪進会が開催されていくことを心より願っております。本年度は,例年よりも多くの方々にご参加いただきました。来年度において,毎年参加される方はもちろん,しばらくご無沙汰されている方,参加されたことのない方も,酪進会でお会いできることを励みに日々,奮闘して参ります。
なお、今年は4年ごとに行っている酪進会総会の開催年です。11月2日(日)を予定していますので、是非ご参加下さい!
末筆ながら、同窓会から助成金をいただきましたことをご報告いたしますと共に、感謝申し上げます。
酪農学園大 ワンダーフォーゲル部OB 人命救助により感謝状受賞
酪農学園大 ワンダーフォーゲル部OB 人命救助により感謝状受賞
雌阿寒岳における遭難救助活動に対して、感謝状を頂戴しました。
(2月2日)、19時25分に捜索開始。読み通りの地点にて遭難者を発見。低体温症の症状が診られたので、ギリギリ間に合ったという状況でした。
北海道の中でも特に寒い阿寒で、厳冬期。遭難者は軽装備。さらには夜から荒天の予報。この状況で翌朝まで生存の可能性は、ほぼ無いと判断。迅速且つ冷静な判断をし行動に移しました。自身の持つ能力を発揮した結果、人命を救えました。
ハローポーターの山岳ガイド(酪農大ワンゲル部OB森下・双樹)が現地に2名いたからできたこと。反省点も含め、今後のガイディングに生きていくと思います。( 95年入部 森下 亮太郎)
十勝毎日新聞に掲載された記事を紹介します。
市川治教授最終講義報告
市川治教授最終講義報告

2月10日(月)午後1時から酪農学園大学C1棟101(旧C10)番教室において、酪農学部農業経済学学科主催による農業会計学研究室市川治教授の最終講義が学生、教職員約80名の出席者により開催された。講義に先立ち相原教授の進行により丸山明学科長の市川教授紹介が行われた。
「農業経済学の今日的課題-TPPのもとでの日本農業の展開の課題-」と題しての最終講義は略歴、役職に加え、教授のこれまでの教育活動、研究活動、学内活動、学会及び社会活動、科研費・競争的資金による研究を年度毎に小冊子にまとめられていた。
日本と北海道農業の今日的課題として1.担い手育成。2.国内自給率。3.原発事故との関連から食の安全・安心等を挙げた。TPPの影響による農業の危機的状況の試算分析や対応について、また農業生産法人の展開の可能性についてPPTにより丁寧に説明した。また循環型農業・酪農の展開と酪農学園大学の役割についてもふれ、「実学教育」に根差した生命を大切にした教育の継続の重要性を説いた。最後にゼミ生やOBからの花束贈呈が行われ、最終講義が終了した。
上田純治教授・小阪進一教授最終講義報告
上田純治教授・小阪進一教授最終講義報告

2月10日(月)10時から酪農学園大学C1棟101(旧C10)番教室において、酪農学部酪農学科 家畜遺伝学研究室 上田純治教授・草地学研究室 小阪進一教授の最終講義が約150名の学生・教職員の出席により行われた。最終講義は寺脇教授の進行で始まり小宮道士学科長が両教授のご経歴を詳細に紹介した。
上田教授の最終講義は「遺伝子マーカーと家畜育種」と題して家畜育種の歴史、免疫・分子遺伝分野の遺伝子マーカー、北海道和種馬やヘレフォード種での遺伝子、DNAマーカーと家畜育種について等について、約50分難解な遺伝子をPPTによりわかりやすく説明した。
最後にはゼミ生から花束が贈呈された。
続いて義平教授の進行による11時からの小阪教授の最終講義は、最初に経歴や研究分野、学園の年表や入学者数推移等を基にして70年代当時の学園の出来事や温室や実験圃場の設置経過等を述べた。
その後に最終講義のテーマである「草地を構成する植物たち」について講義した。混播での刈取高や頻度、草種の組合せによる影響、雑草の出現頻度、元野幌農場での牧草地植生改善等についてPPTを用いて実験結果データを報告した。
退職にあたり、学生指導等教育研究専念への改善を要望した。会場には多くのOBOGが集まり、最終講義を熱心に聴講していた。ゼミ生やOBからの花束贈呈のあと、関係者により集合写真撮影が行なわれた。
酪農学園短期大学第2部酪農科2期同期会報告
酪農学園短期大学第2部酪農科2期同期会報告
2014年2月1日、午後6時30分より札幌ジャスマックプラザホテルにおいて同期会が開催され、1968年の卒業以来46年振りに会う懐かしい友もいて、遠くは新潟県の2人を含め、全道各地より25名の参加者で催されました。
小針幹事の挨拶に続き、95名の卒業生の中、すでに亡くなった13名の友に黙祷を捧げ、新潟の小林君の乾杯の発声で開宴となりました。
学生時代の思い出話や後継者不足と農政に翻弄されている農村の現実の中での近況報告がされ、今、現役で農業を行っている者、また議会活動やJAの役員として公的に頑張っている者、更には悠々自適の生活を送っている者等さまざま。
しかし、それぞれが今日ここで元気で同期会に参加出来る事に感謝しながら、在学時代にタイムスリップして友との絆を強め、時の経つのも忘れ楽しい時を過ごしました。
次回は3年後、北見地区の仲間が幹事となって、開催する事を決め、お互いが健康管理に十分注意して、再会を誓い閉会となりました。(文責 幹事 梶 英明)
加藤清雄教授最終講義報告
加藤清雄教授最終講義報告

1月24日(金)午後2時から加藤清雄教授(獣医学科獣医生理学ユニット、獣医保健看護学類動物理学療法学ユニット)の最終講義「反芻動物の生理学的特性」が中央館学生ホールにおいて開催された。教職員や学生、そして遠路駆けつけた同窓生により会場は埋め尽くされた。

「酪農学園大学との出会い」で紹介された若き日の写真は、何と酪農学園大学の受験票に添付された写真であった。入学後直ちに牛島教室に出入りし、ゼミ副読書「乳牛の科学」の序に記されていた梅津教授の言葉に感銘を受け東北大学大学院に進学し、1977年に農学博士の学位を取得後、直ちに本学に赴任したことが紹介された。
最終講義のテーマである「反芻動物の生理学的特性」については、ご自分の研究により明らかにした特性として、反芻動物の膵外分泌がVFAにより刺激されること(Am. J. Physiol.)、またVFAの吸収にはモノカルボン酸輸送体が関与していること(J. Physiol.)が、アニメーションを駆使してわかりやすく紹介された。
反芻動物の膵外分泌に関する研究では、日本畜産学会賞を受賞され、また国際反芻動物生理学シンポジウムで招待講演をされ、2つの目標がかなえられた喜びを語られた。
獣医生理学教室は、外国人留学生の絶えない研究室で中国から3名、韓国から1名、ポーランドから3名、エジプトから1名と合計8名の留学生により研究が支えられたこと、これは33才という若さでアルバータ大学に留学する機会を与えられたことにより国際感覚が養われ、多くの留学生を受け入れることにつながったと述べられ、謝意が表された。
講義で大切にしたことや「人を愛する教育」として積極的に学生と話し、学生の名前を覚え、学生を知ろうと努力されたことが紹介された。研究室の若き同僚として青木道子先生、峯尾仁先生、翁長武紀先生、井上博紀先生、林英明先生、椿下早絵先生に支えられたことに謝意が述べられた。また、馬術部とYOSAKOIサークル「祭」の顧問として、もう2つの研究室という思いで学生の活動をサポートしたことが紹介された。

最後に「The last challenge in the RGU」として、人前では吹いたことのないフルート演奏にチャレンジされた。曲は「酪農讃歌」で、間に「アメージング・グレース」を挿入し、神の恵み、出会ったすべての人、すべてのことに対する感謝の気持ちを表された。
講義終了後、獣医生理学ゼミ、動物理学療法学ゼミ、大学同級生、卒業生から花束の贈呈があり、加藤教授から、出席者へ感謝の言葉が述べられ、最終講義を終了した。(文責 林 英明)
松中照夫教授最終講義報告
松中照夫教授最終講義報告

1月17日(金)午後1時から松中照夫教授(土壌作物栄養学研究室)の最終講義「土壌肥沃度論」(循環農学類農学コース3年)が大学C5-201番(旧南20)教室において開催され、学生、教職員約70名が出席した。くしくも1月17日は19年前の1995年阪神淡路大震災の日でもあり、兵庫出身の先生はこの年4月に本学に着任したとのことでした。
最初に先生から学生に対して授業「土壌肥沃度論」の第15回目を最終講義とすることが述べられた。また関係者に配付された最終講義‐授業「土壌肥沃度論」-の小冊子には教授の略歴、学位、受賞に加えて、教育活動として1995年度から本年まで指導された卒業論文・修士論文・博士論文の題目や海外からの留学生の受入報告。研究活動として学術雑誌論文、著書、各種研究会・学会の招待講演、海外出張一覧。社会活動として各種講習会・講師依頼、学会および社会活動が詳細に掲載されている。
最終講義は、「健土健民」と土壌肥沃度について述べた。科学(Science)として見た場合の「健土」とは何か。「土」「肥沃度」の定義も含めて丁寧に講義された。「健土」の条件として物理的性質の1)厚みと硬度 2)水分 科学的性質の3)pH 4)養分 の4つの条件について、作物栽培上、定量的に測定する必要があり本学附属農場の土壌の問題点を含めて講義した。
土壌の物理的性質を直すことを「木を植える人」を譬えて無私で種を植え続けることの重要性を説いた。「土」は基本的条件がわかっていれば、何世代か先の為にひたすら努力することにより改善されると述べた。また本学の教育研究活動も教員と職員がスクラムを組んで学生の為に実践しているとも語った。
講義終了後、小宮道士循環農学類長からの松中先生へのお礼の挨拶のあと、松中ゼミの学生や卒業生から花束の贈呈があり、松中教授から、出席者へ感謝の言葉が述べられ、最終講義を終了した。
森川純教授最終講義報告
森川純教授最終講義報告

1月15日(水)森川純教授(地域国際関係論研究室)の最終講義(環境共生学類2年科目「国際関係論」)が10時40分からA3号館201番教室で開催され、約150名の学生、教職員が出席しました。
1997年12月本学の環境システム学部設置時から地域環境学科教授として赴任した森川先生は、最終講義では少年期から現在に至るまでの自己体験を踏まえて、学びにおける大切な要点等について述べました。また2014年は第一次世界大戦からちょうど100年を迎えた年でもあり、戦争体験等記憶の継承の大切さも語りました。
森川ゼミは国際感覚を養った卒業生を多数輩出しています。最終講義では、少年期に与えられた一冊の「世界地図帳」から学んだ知的好奇心の大切さや、感動が興味関心を増大させ、勉強から知を力にするための更なる学びを行った高校時代のこと。点から線、線から面、面を立体的に重ねた鳥瞰図的思考の重要性をいつものように穏やかな口調で講義しました。
大病での入院生活の末に遂げた自己変身(self reflection)とその後のデンマークやナイジェリアでの留学生活の中から、現実を見据えながらの理想に向かって試行錯誤することの大切さや同時代感覚・当事者感覚を持つことの大切さを話しました。
帰国後は「世界システム論」の分析枠組みを論稿し、大学院でアフリカと日本の関わりを学ぶ機会を得て、研究者としての歩みが開始しました。
アフリカ国際関係論の分野では人種差別政策や日本との関係究明作業を内外誌に論稿され、その後、勤務したオーストラリアのアデレード大学では日豪関係に関する研究にも従事しました。本学では日本外交と象牙問題とNGO等や野生生物保全問題にも取り組み、捕鯨問題にも論稿されました。
講義終了後、森川ゼミの学生代表花束の贈呈があり、最後に森川教授より、出席の方々へ感謝の言葉が述べられ、最終講義を終了しました。
細田治憲氏(短大9期・大学酪農1期)、角倉了一氏(機農高酪農経営4期)宇都宮賞受賞決定。
細田治憲氏(短期大学酪農科9期・大学酪農1期)、角倉了一氏(機農高酪農経営4期)宇都宮賞受賞決定。
公益財団法人宇都宮仙太郎翁顕彰会(北良治理事長)は、1月9日(木)理事会・評議員会において「第46回宇都宮賞」の表彰者を決定した。
3部門の中の「酪農経営の部」には由仁町細田治憲氏(短期大学酪農科9期・大学酪農学科1期生)が、「乳牛改良の部」では大樹町角倉了一氏(機農高校酪農経営科4期生)がそれぞれ受賞することが決定した。
表彰式は宇都宮仙太郎翁の命日である3月1日(土)14時から札幌パークホテルにおいて開催される。同窓生の表彰に心よりお祝い申し上げます。